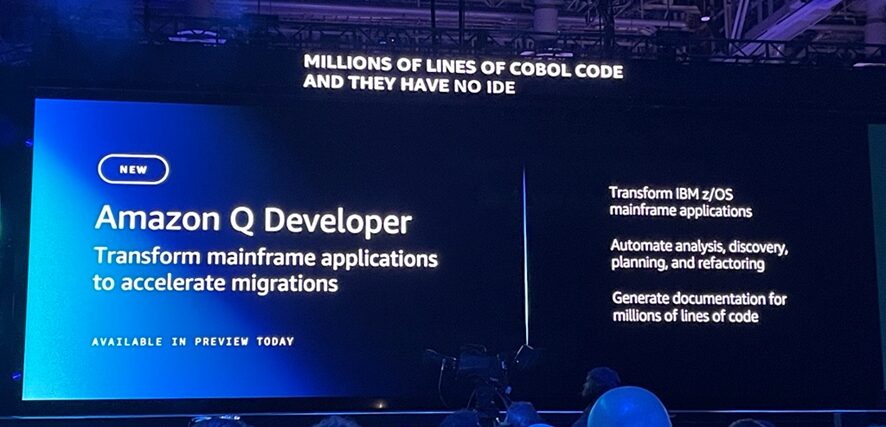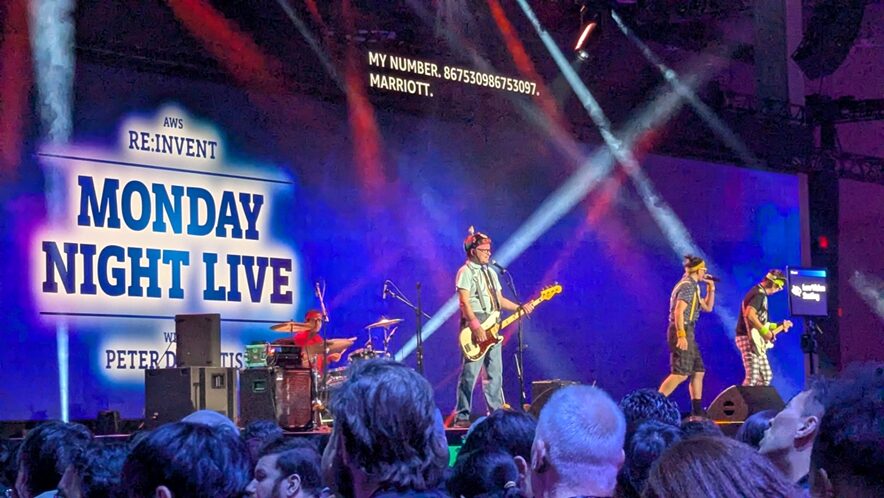オンプレからRDS移行の勘所――第1回 バックアップ設計

はじめに
クラウドシフトが加速する昨今、ビジネスの現場では従来のオンプレミス環境からクラウドサービスへの移行が大きなテーマとなっています。特にデータベースシステムは、安定性やスケーラビリティ、コスト面など、さまざまな理由からクラウド化への関心が高まっています。
本ブログでは、オンプレミスのDBサーバーからAWSのRDS(Relational Database Service)への移行に関する注意事項について、シリーズで詳しくご紹介していきます。これから移行を検討されている方や、実際にプロジェクトを進めている方にとって、役立つ情報をわかりやすくお伝えしていきますので、ぜひご期待ください。
第1回目となる今回は、「バックアップ設計」について取り上げます。
バッチ運用/バックアップ設計の見直しの必要性
オンプレミスからAWSへのマイグレーションの案件において、DBサーバーをAWSのRDS(Relational Database Service)へ移行する際、従来サーバーで直接稼働していたバックアップやログ管理などのバッチジョブの運用方法を大幅に見直す事例がありました。
これは、RDSがAWSによるマネージド型サービスであるため、OSやDBシステム領域への直接的なアクセスやコマンド実行の自由度が大きく制限されているためです。
そのため、従来の運用バッチを一旦すべて洗い出し、それぞれの内容・目的を明確化し、そのうえで新しい運用方法や技術に置き換えることが不可欠でした。
バッチ運用/バックアップ設計の見直しポイント
まず最初のステップとして、現行DBサーバー上で稼働中の全バッチジョブを一覧化し、例えばDBフルバックアップ、ログの保管やローテート、データ抽出といった個別機能ごとに、ジョブの目的を分類します。
そして次に、RDS標準の自動バックアップやスナップショット作成、トランザクションログの自動保存といった機能でどこまで置き換え可能かを検討します。多くの場合、DB全体のバックアップやPITR(時点復旧)等はRDS標準機能で対応でき、サーバー自体のOSやシステムディレクトリ直アクセスが前提の処理は不要か、もしくは外部ツールやサービスに再構築することが求められます。
RDSシステム自体はOSレベルでの操作(シェルスクリプト実行など)が制限されているため、従来DBサーバー上で実行していた運用スクリプト類は、他サーバーからの処理実行や、AWS Lambdaなど外部実行基盤に実装し直すなどの必要があります。また、従来型の「ジョブ管理ツール」からEventBridgeによるスケジュール管理や自動実行に置き換えれば、運用負荷・工数の大幅削減も見込めます。
また、RDS本体や運用バッチのモニタリングはAWS CloudWatchなどを活用して一元化することで、障害検知や運用データの可視化・分析が容易となります。ただし、既存バッチをAWS上で再設計・外部化することで、システム全体のジョブ数増加や依存関係の複雑化、運用属人化といった新たなリスクが発生する場合もあります。そのため、十分な運用ドキュメント整備と標準手順化、テストケース設計により、運用の品質・安定性向上にも注力すべきです。
まとめ
オンプレミスDBサーバーからRDSに移行した際は、バックアップやログ取得などの既存バッチジョブをRDSの標準機能やAWS各種サービスと連携するかたちで最適化し、既存ジョブ棚卸し、機能ごとの置き換え可能範囲の見極め、バッチ外部化設計、運用監視の高度化を計画的に進めることが、クラウド運用の信頼性・効率化への鍵となります。
RDSへの移行や運用最適化についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。