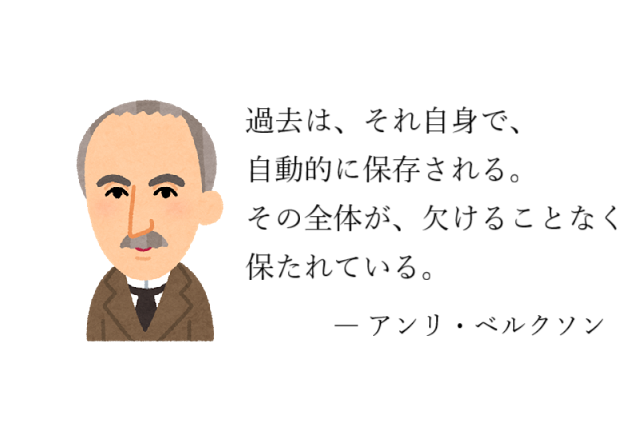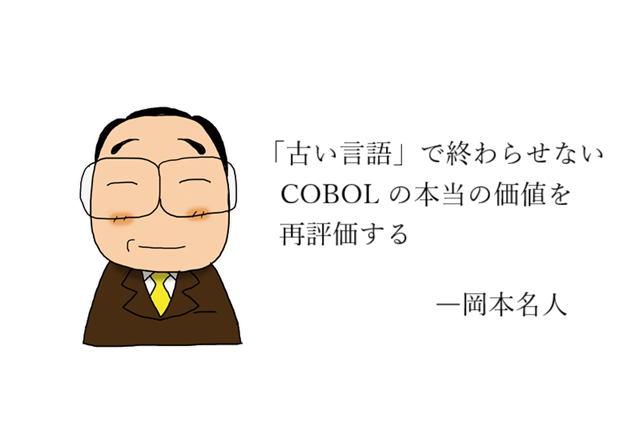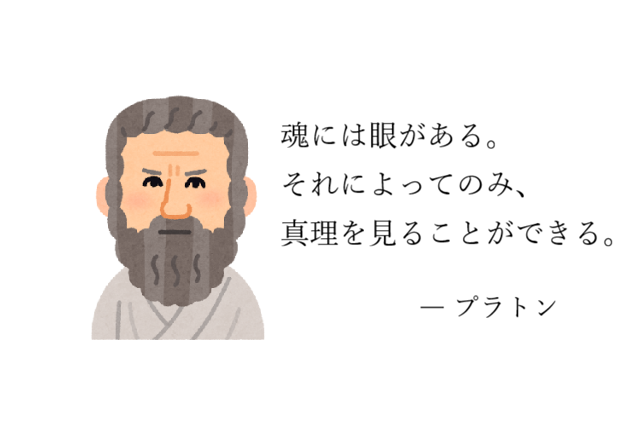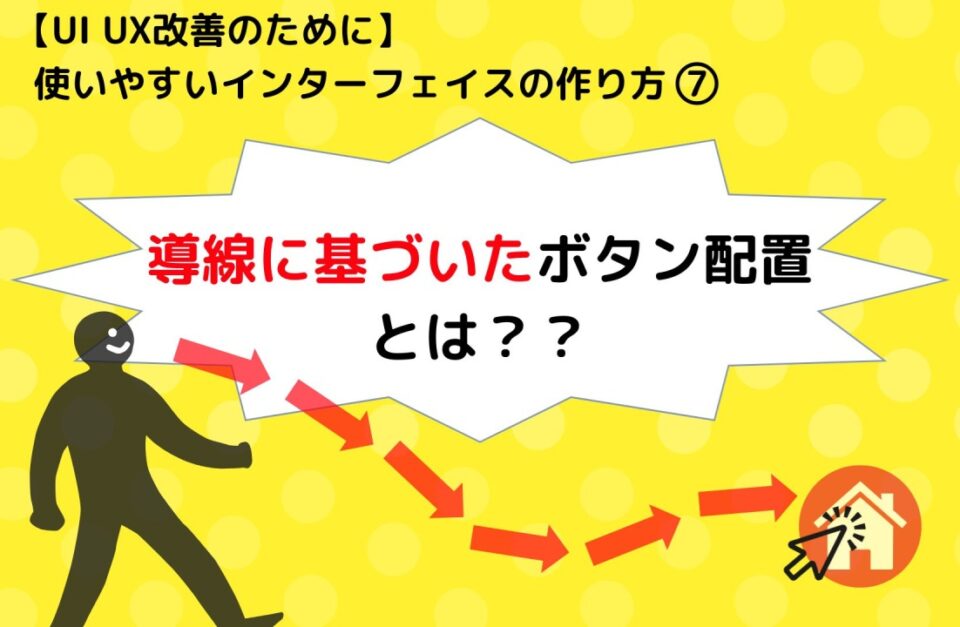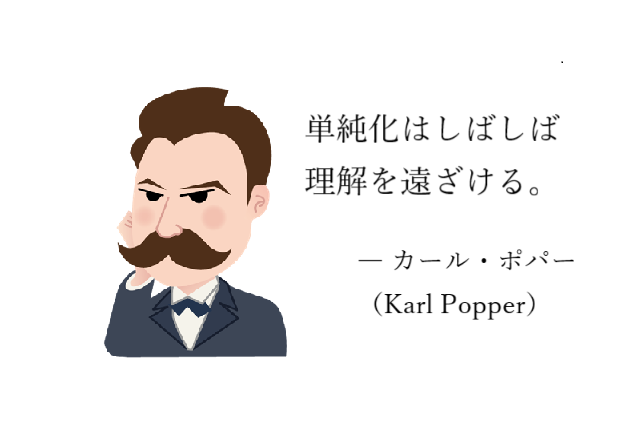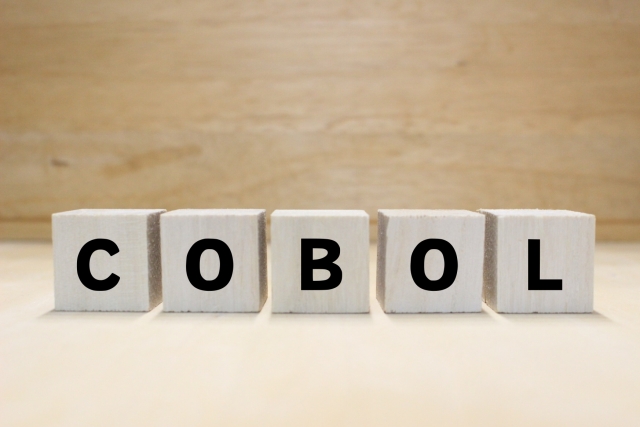なぜ「全部捨てるDX」は危険なのか?──レガシーシステムに宿る経営の知恵【レガシー侍】
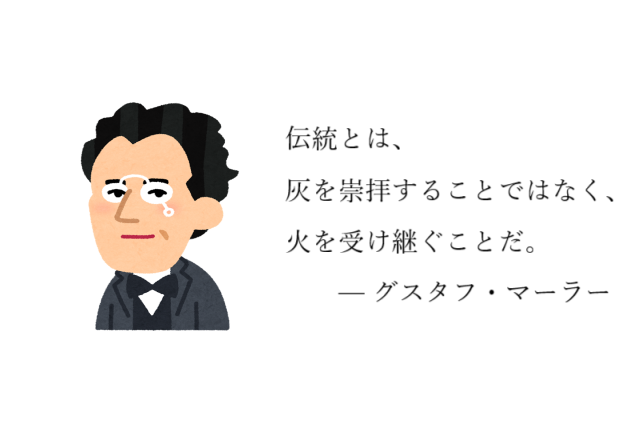
「伝統とは、灰を崇拝することではなく、火を受け継ぐことだ。」
— グスタフ・マーラー
近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)やシステム刷新の一環として、既存システムを全面的に置き換える「ゼロリプレース」を選ぶ企業が増えています。
新技術の導入や業務の効率化を目指す姿勢は重要ですが、その一方で、長い時間をかけて築かれてきたシステムや運用には、目には見えない知恵や判断が息づいています。これを無視してしまうと、刷新後に意図せぬ混乱や機能不全を招く可能性があります。
なぜITは過去を捨ててしまうのか?
ITの世界では、「古いものは非効率」「新しいものが最適」という考え方が支配的になりがちです。
特にERPやSaaS導入時の「Fit to Standard(標準への合わせ込み)」は合理的に見えますが、企業が独自に培ってきた判断や業務の流儀を切り捨てる危険性を含んでいます。たしかに業務の標準化やスピード向上には寄与しますが、「なぜこのやり方が生まれたのか」という背景ごと消してしまう危うさがあるのです。
実際の現場には、マニュアルには記されない工夫や例外判断が存在しています。
「この顧客のケースではこう対応する」「この数字には過去の背景がある」──そうした暗黙知は、表に現れないながらも企業の日常を支える重要な基盤です。
一足飛びの刷新が抱える不確かさ
全面的な刷新プロジェクトは、スムーズに見えても、実態は複雑です。
既存システムをすべて捨てて新しくする場合、全仕様を一から定義し直す必要があります。しかし、多くの企業では、現場で培われた判断や例外処理が明文化されていません。そのまま新システムへ移行すると、現場では「使いにくい」「細かな対応ができない」といった声が上がり、結果的にExcelや紙による補助運用が増え、「DXのはずが手作業が増えた」と現場が疲弊するケースも少なくありません。
刷新とは本来、「古きを否定する行為」ではなく、何を未来へ継承するかを丁寧に見極める営みであるべきです。
破壊ではなく、継承という考え方
モダナイゼーションとは、新旧を断絶させる行為ではなく、これまでの営みの中から価値を見つけ、それを次の仕組みへと 継承するプロセス です。
重要なのは、「何を手放すか」よりも、「どこに本質的な価値が宿っていたのか」を見極め、その価値を未来の仕組みの中に生かす視点です。
変革の本質とは、過去を清算するのではなく、過去を素材として未来をかたちづくることにあります。
酒蔵の例に見る“失われた価値”
ある老舗酒蔵は、衛生面と効率向上を目的に、古い蔵を解体し最新設備の工場を建てました。
しかし、酒の味は微妙に変化しました。蔵に長年棲みついていた菌や空気の流れが、酒の風味を形づくっていたのです。
見た目やプロセスを新しくするだけでは再現できないものがある──効率だけでは測れない価値が、確かに存在するのです。
ITにも「継承の文化」を
システム刷新も同様に、“技術だけではないもの”をどう未来へ渡すかを考える視点が重要です。
どの判断が組織を支えてきたのか
どの例外が現場の安全弁となっていたのか
どの不便が、逆に人の知恵を育てていたのか
DXとは、こうした「見えない知恵」を未来の仕組みに翻訳する営みなのです。
おわりに
DXを成功に導く鍵は、「何を新しくするか」ではなく、「何を受け継ぐか」を見極めることです。DXやシステム刷新は、過去を切り捨てるためではなく、新しい未来を築くための活動です。
そのためには、「大胆な刷新」よりも、「確かな継承」を軸に置くことが、結果として企業の強さにつながります。
レガシーに宿る静かな知恵を尊重し、未来へ引き継ぐ──
それは保守ではなく、最も堅実で、最も成熟した変革の姿ではないでしょうか。