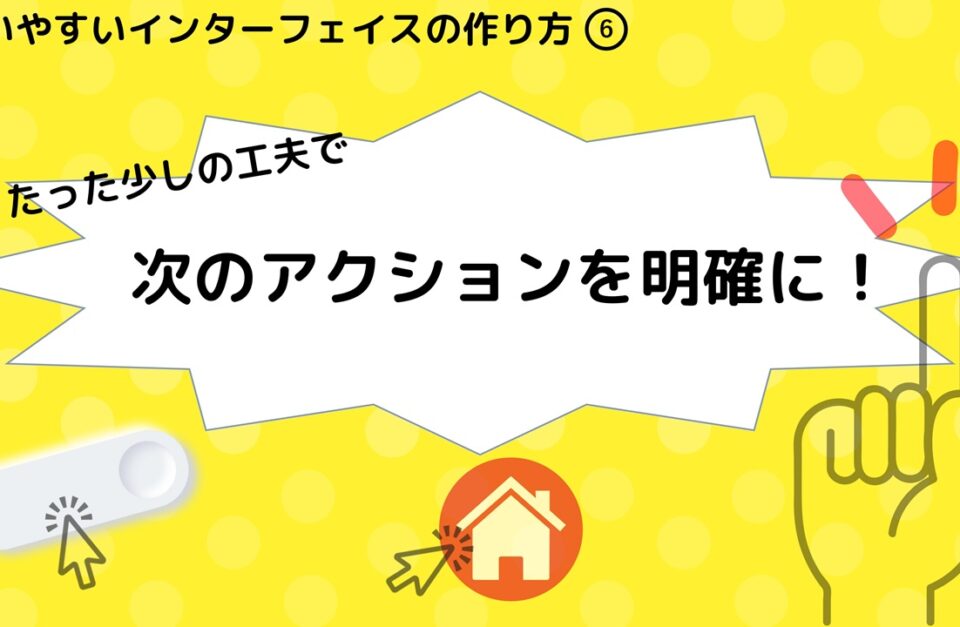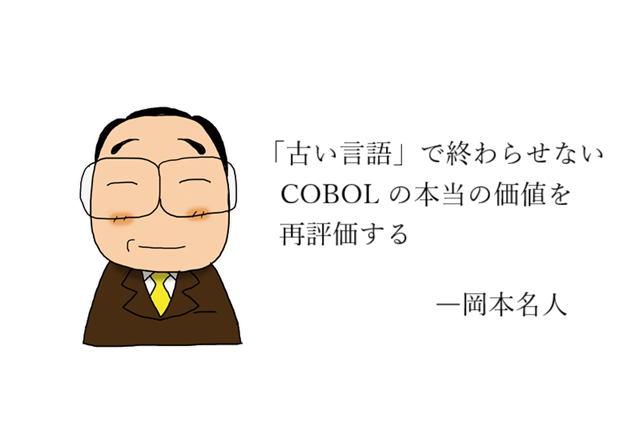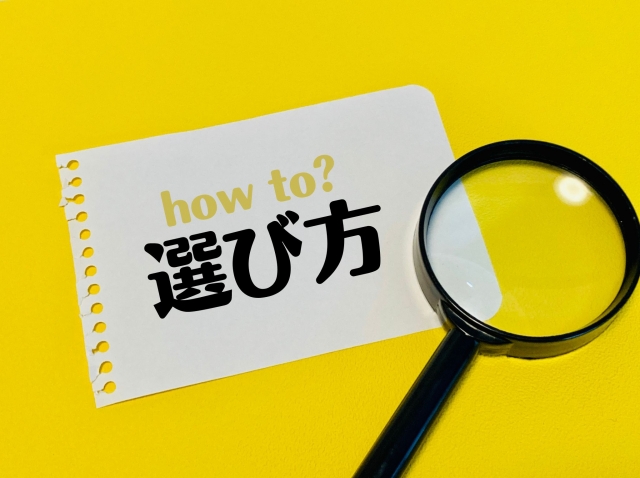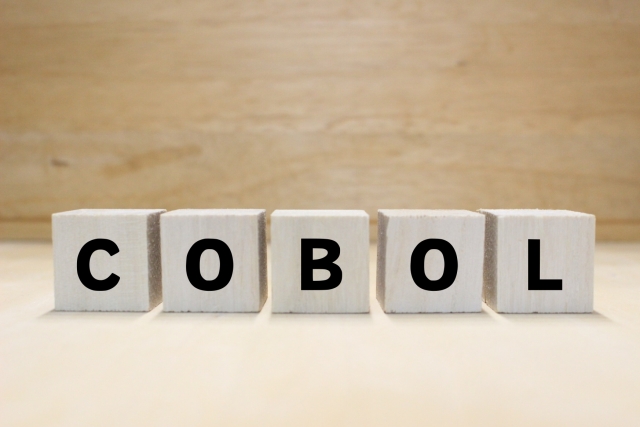PHPマイグレーションの進め方 -後編-
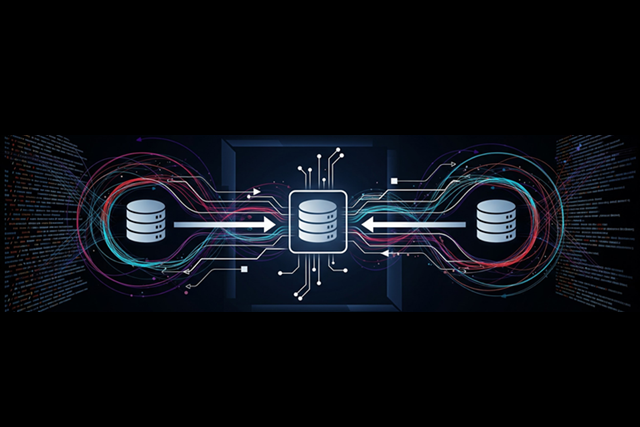
はじめに
PHPアプリケーションのマイグレーションは、パフォーマンスの向上、セキュリティ強化、新機能の利用を可能にする重要なプロセスです。この記事では、PHPマイグレーションを成功させるための主要なステップと考慮事項について前編と後編に分けて解説いたします。
後編では、PHP/Laravel マイグレーションの成功への秘訣について解説いたします。
「PHPマイグレーションの進め方 -前編-」については以下を参照願います。
https://tech.systems-inc.com/column/detail/data-8399/
PHP/Laravel マイグレーションの成功への秘訣
システムの棚卸とスリム化
まずは、マイグレーションに着手する前に、現行のPHP/Laravelシステムの詳細な棚卸が必要です。
システム規模の把握
ソースコードのステップ数、ファイル数、画面数、バッチ処理数などを把握します。
使用技術の洗い出し使用しているPHPバージョン、Laravelバージョン、Composerで管理されている全依存ライブラリ、データベースの種類とアクセス方法、連携している外部APIなどを詳細にリストアップします。
特に古い、あるいは特殊なライブラリ・フレームワークの使用有無を確認します。
不要コードの排除(スリム化)
長年運用されているシステムには、使われていない機能やテストコード、過去のバックアップなどが含まれていることがあります。
これらを事前に特定し、マイグレーション対象から外すことで、プロジェクトの規模を抑え、コスト削減につながります。
ただし、スリム化自体の工数と削減できるマイグレーション費用を見極める必要があります。
移行性検証 (Feasibility Study)
本格的な移行作業に入る前に、システム資産の一部を対象とした「移行性検証」を実施することが非常に重要です。
サンプリング
システム全体を代表するような、様々な機能、複雑なコード、特に古いライブラリを使用している部分などをサンプリング対象として選びます。
機能単位に移行するなどスモールスタートする際に有効です。
実際の移行作業
選定したサンプルに対して、PHPバージョンアップ、Laravelバージョンアップ、依存ライブラリのアップデートといった実際のマイグレーション作業を行います。ここで修正、コーディングルールなどを決めておくと良いでしょう。
課題の特定
この検証を通じて、自動変換ツールで対応できないコードパターン、依存ライブラリの互換性問題、予期しないエラーや挙動の変化、古いPHP/Laravelの書き方から新しい書き方への修正の難易度などを具体的に把握します。
計画と生産性の向上
移行性検証で得られた知見を、残りのシステムの移行計画や作業手順に反映させ、より正確な見積もりや効率的な作業方法を確立します。
サードパーティ製品(PHP依存ライブラリ)への対応
移行性検証や棚卸しで特定された、新しいPHP/Laravel環境に対応しない依存ライブラリについて、代替ライブラリの検討、新しいバージョンへのアップグレード、または機能の作り直しを計画します。
品質確保と現新差異の管理
マイグレーションの目的は「現行システムと同じ挙動」を新しい環境で実現することです。
比較テスト
移行後のシステムが現行システムと同じ挙動を示すかを徹底的にテストします。入力フォームのバリデーション、データの処理ロジック、データベースの更新内容、帳票出力などが含まれます。
現新差異の特定と承認
PHPバージョンやライブラリの仕様変更により、完全に同じ挙動にならない現新差異が発生する可能性があります。
例えば、数値計算の丸め処理の違い、文字列処理の挙動変化、新しいライブラリでの描画や出力形式の違いなどが考えられます。
これらの差異を事前に特定し、その影響範囲をお客様と共有・承認しながらプロジェクトを進めることが不可欠です。
テストシナリオ
機械的なコードレベルのテストだけでなく、実際の業務の流れに即したテストシナリオを顧客と協力して作成し、実行することが品質向上に繋がります。
専門知識とツールの活用
PHP/Laravelのマイグレーションも、特定のバージョン間の非互換性や複雑な依存関係の問題を解決するには専門的な知識が必要です。
独自のツールを活用したり、過去の経験に基づいたパターン分析を行える専門家(ITベンダー)のサポートを受けることも有効な選択肢です。
自動化ツール(Rector等)の活用に加え、手修正が必要な箇所を効率的に特定・修正するためのノウハウが重要となります。
まとめ
PHPマイグレーションは複雑な作業ですが、慎重な計画と実行により、アプリケーションの将来性を確保し、より良いユーザーエクスペリエンスを提供することができます。
検討する際には、ぜひ一度お問い合わせください。
資産の規模や利用サードパーティー製品などのヒアリングをさせていただいたうえで概算見積を出させていただきます。もちろん見積費用は無料です。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。